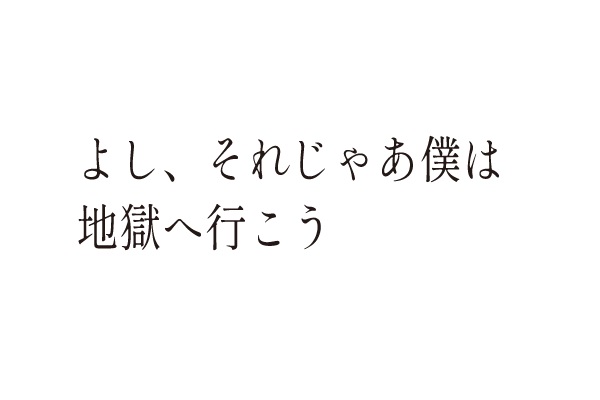アメリカでまだ奴隷解放宣言(1863 年)が出されていなかった 1830 年頃の南部の奴隷州イリノイ州から始まる『ハックルベリイ・フィンの冒険』は、突如姿を現した父親による虐待と、社会が押し付ける規範から逃れようとする主人公のハックことハックルベリイ少年が、奴隷を酷使する深南部に売り払われてしまうのを恐れて逃亡する黒人ジム——ハックが養子として暮らしていた家の奴隷——と共にミシシッピ河を筏で下っていく物語です。
二人とも逃亡者ですが、ジムの「追手」はハックのものとは性質が全く異なっています。ハックはいわば「家出」をしているのに対して、奴隷制が認められている州では「逃亡奴隷」を逮捕することは役人の義務だったのみならず、白人であれば誰でもそうする権限がありました。懸賞金もかけられました。そんなジムの逃亡をハックは助け続けます。
しかし、ハックはたびたびジムを密告しようとしていました。その時のハックは、自分が逃亡奴隷の手助けをしたことが世間に広まったら恥ずかしくて顔もあげていられないと考えてさえいます。そのような「悪行」に手を染めて「地獄行き」が確定してしまうことに震えて怯えながらも、ハックは「よし、それじゃあ僕は地獄へ行こう」と決断します。白人が黒人と親しくするだけでも非難された時代にあって、物語の山場であるこの場面に、友情に突き動かされたハックの葛藤の末の「勇気」を読み取りたくなります。
ですが、とても不思議なことに、密告しなかったのは自分には「兎ほどの勇気さえなかった」からだ、とハックは感じています。通常、私たちは、「正義」を行うには「勇気」が必要だと考えます。行われている不正に対して見て見ぬふりをするのは「臆病」で、声をあげるのが「勇気」ある行動だとされているでしょう。ハックには「声をあげよ=密告せよ」という「正義」の声が聞こえていたわけです。実に「正義」それ自体がレイシズムという不正によって培われていたのです。
私たちにはいつの時代もその時代に応じた「正義」が押しつけられているものです。そんな「正義」のために誰かを密告する「勇気」など私たちは持ちたくありません。多くの人が「正義」とみなすものを行うための「勇気」を、しかし状況によっては疑う知性が必要であることを、作者マーク・トウェインは標題のことばによって私たちに教えてくれているようです。