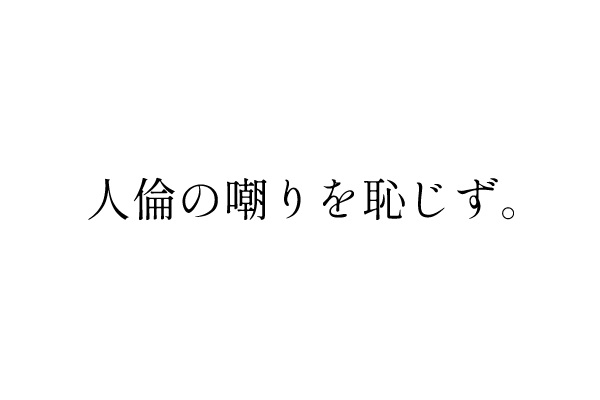親鸞(1173~1262)は、主著である『教行信証』に、「人倫の嘲(あざけり)を恥じず」(「化身土巻」)、さらには「人倫の哢言(ろうげん)を恥じず」(「信巻」)と繰り返し述べています。
標題にあるこの言葉は、「たとえ多くの人から、嘲りを受けようとも、恥じることはありません」という強い決意の言葉です。ここで嘲りとは当時の仏教界や社会のものの見方、つまり世間を支配する常識や「空気」といったものに疑問をもち、自分が本当に大切だと思う道を歩むことによって受ける批判をいいます。
親鸞が四十二歳の時、天候不順による干ばつなどで飢饉が発生した中で、衆生救済の為に、浄土三部経という大部な経典を千回読誦(どくじゅ)しようと決心しました。しかし四、五日経って、念仏以外に何の不足があってお経を読誦しているのだと思い返し、中断します。その当時の仏教界では雨乞いや国土の安泰(あんたい)を願い祈祷(きとう)を行うことは当然のことでした。人の為、社会の為に少しでも役に立ちたい、苦しむ民衆の期待にこたえたいと思う僧侶なら誰しもが行ったはずです。しかし、親鸞はそこに本当の仏教があるのかという疑問をもち、人間はいつか病に倒れ、老い、そして死ぬ。その事実から目を逸らし、少しの寿命を延ばすためや、自身の欲望や願望を満たすため、ましてや雨を降らせるために仏教があるのではない。生老病死の現実を、その苦悩の中に在って、その一度限りのいのちを生き生きと生き抜く力と勇気をたまわるものではなかったのかと。
こうしたエピソードに限らず親鸞の切り開こうとした道は、その当時の時代社会のなかで、容易に受け入れられるものではありませんでした。親鸞は仏教界の常識や社会を覆う「空気」にどうしても身を任すことができず、自分自身と真向かいになり、本当にこれでいいのかと、自身の内に生じた違和感を持ち続け、問い続けたのです。その親鸞の愚直なまでの歩みは、現代を生きる私たちにも、「あなたはそれでいいのですか」という問いを投げかけるものであると同時に、勇気を与えてくれます。
周りの評価や流行が気になり、自分自身の思いや意見を表現することに躊躇(ちゅうちょ)していないでしょうか。社会の「空気」を忖度してしまい、周りに合わせようと努力して疲れ切っていないでしょうか。自分の内にある違和感に正直になり、立ち止まることで、「空気を読め」と言われたり、「ノリが悪い」と批判されるかもしれません。しかし、自己を見失い流され続ける虚しさに気づき、立ち止まることへの不安の中で、自分自身を取り戻す勇気こそが求められているのではないでしょうか。