仏教教育センター
きょうのことば
きょうのことば 2026年3月
一切衆生病むを以て、是の故に我も病む。
SEARCH
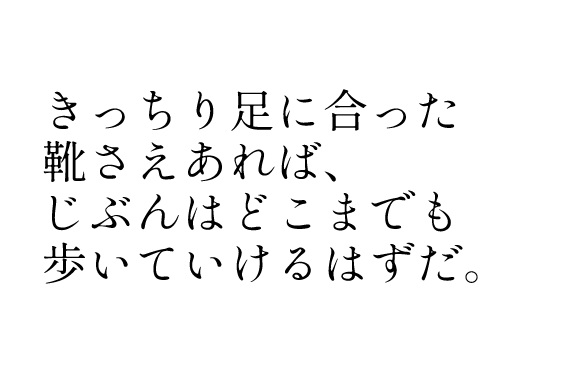
きっちり足に合った靴さえあれば、じぶんはどこまでも歩いていけるはずだ。
須賀敦子(1929 - 1998)は『ミラノ 霧の風景』『コルシア書店の仲間たち』『ヴェネツィアの宿』など有名な代表作があるエッセイ作家です。また、イタリア語、イタリア文学についての膨大な知識から、イタリア文学翻訳家としても活躍しました。
須賀は第二次世界大戦中に多感な思春期を過ごしました。彼女はカトリック系の学校に学んでいましたが、神の存在を信じる友人に「なぜ、神様など信じるのか」と問いかけるような子どもでした。父親の事業や戦争の影響で関西—東京間の引っ越しを何度か重ね、自らの環境や時代の空気に馴染めない自分に気づきます。須賀は「自分は何者なのか」と迷い人生を模索します。当時の女性は、学校を出たら結婚し妻となり、母となることが当たり前とされており、こうした当時の空気にも息苦しさを感じていたのかもしれません。
その後、フランス留学の機会を得ますが、須賀はそこでも馴染むことができませんでした。しかし、フランス滞在中に訪れたイタリアに惹かれるようになります。一度は日本に帰国しましたが、1958年に再びイタリアへ出発します。1960年に夫となるイタリア人と出会い、その結婚生活を通して、生活者としてイタリア、そしてキリスト教文化に理解を深めます。しかし、結婚してわずか7年で、心から信頼し理解し合った夫を亡くします。こうした絶望を経験しながらも須賀は「自分は何者か」「自分にしかできないことは何か」と問いながら人生を歩み、50代半ばから上記のようなエッセイをまとめました。
冒頭の「きっちり足に合った靴さえあれば、じぶんはどこまでも歩いていけるはずだ。」の後には「そう心のどこかで思いつづけ、完璧な靴に出会わなかった不幸をかこちながら、私はこれまで生きてきたような気がする。」とあります。
確かに自分の足に合わない靴を履いて歩き出すと、どうもうまく歩けない。こうした「合わない靴を履いて歩く」かのように、私たちも自分の人生が思うように進んでいないと戸惑い、立ち止まることがあるかもしれません。私がいるのはここではなかったのかも。ここにいるのは、完璧な靴に出会わなかったからだ、と諦めてしまうかもしれません。
もしかすると、人生では「きっちり足に合った靴」というものは見つからないのかもしれません。けれども大事なのは、たとえ今が想定外の人生であったとしても、私たちが「きっちり足に合った靴」を探してみよう、と一歩前に踏み出すことなのかもしれません。そうすれば、考えたこともない「新しい靴」が実は自分に合う、という発見もあるでしょう。そうして迷いながらも新しい一歩を歩み出した時には、合わなかった靴はいつの間にか「きっちり足に合った靴」となり、どこまでも歩いていけるようになり、そしていつか、自分の行きたかったところにたどり着くことができるのだと思います。