仏教教育センター
きょうのことば
きょうのことば 2026年3月
一切衆生病むを以て、是の故に我も病む。
SEARCH
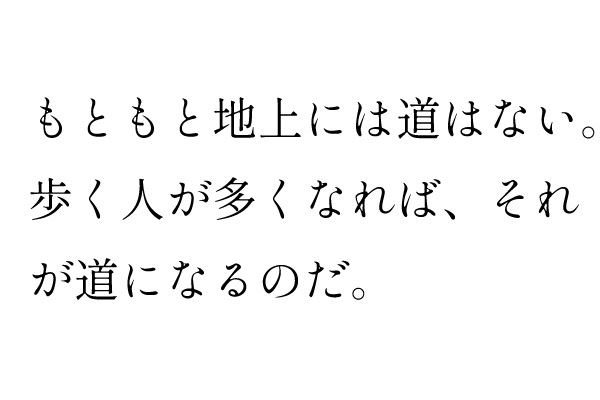
もともと地上には道はない。歩く人が多くなれば、それが道になるのだ。
標題のことばは、中国近代文学の礎(いしずえ)を築いた魯迅(ルーシュン)<ろじん1881-1936>の短編小説「故郷」(1921)の結びにおかれた一節です。日本でも、多くの国語教科書に採用されてきたこの名作を通して、激動期の中国社会で懊悩(おうのう)する人びとの姿につよい印象を受けた読者も少なくないでしょう。作品全体に貫かれている寂寞(せきばく)の悲哀は、時の移ろいに押し流される私たちにとっても、やはり同じようにこみ上げてくる切なさのように感じられ、主人公たちへの共感を誘っているようにも思われます。
簡単にあらすじをおさらいしておきましょう。出世を果たし、20年ぶりに帰郷した「私」は、記憶のなかの美しい故郷がすっかり様変わりしたことに胸を痛めます。語り手の「私」自身もまた、家の没落のために一族の屋敷を売り渡し、彼が暮らしを立てている異郷の地に母や甥を迎えようと、故郷に永遠の別れを告げるために帰ってきたのでした。「私」が再会を楽しみにしていた幼なじみの閏土(ルントウ)は、荒れた世の中で貧困にあえぎ、辛苦をくぐり抜けるなかで、かつての輝きを失っていました。兄弟同然の仲だった二人の間は、すでに厚い壁で隔てられていることに「私」は悲嘆します。そんな中、甥の少年と閏土の息子との間には早くも友情がめばえていることに気づき、せめて若い世代は、自分たちが味わうことのなかった新しい人生を歩んでほしいという希望を抱きながら、「私」は故郷をあとにします。将来その希望が現実になるか否かは、これからの行動次第であり、多くの者が希望を信じ、前へと進んでいくことで新たに道は拓かれ、踏み固められていきます。
魯迅は、けっして明るくはない短編をこのように力強く前向きな展望で結びました。とはいうものの、この結びの一節を、いわば「赤信号みんなで渡れば怖くない」といった態(てい)で解釈してしまえば、ミスリードになるでしょう。人びとが状況への意味づけ次第で行動を定め、その積み重ねによって現実の世界も変わっていくのだといった楽観視を魯迅がしていたわけではないからです。「地上の道」と比喩的に重ねられている「希望」は、ここでは大きく二つに分けられます。ひとつは、閏土の希望のように、庶民が日々の生活の困窮から抜け出そうと願う現実の足元にある希望であり、他方は、「私」のように、国の将来を憂い、理想の社会を打ち立てようと知識人たちが目指す、はるか遠くにある希望です。魯迅もまた同様の希望を抱き、文学による社会変革に身を投じた知識人でした。
「故郷」という短編は、魯迅自身の経験をもとにした作品ですが、その時代背景には、伝統的帝国の清朝から近代的国民国家の中華民国、さらに中華人民共和国へと中国が大きく変貌を遂げようとする歴史のうねりがあります。近代国家建設という理想を高らかに掲げながらも、何ら変わらない現実の重さに打ちひしがれ、変革に主体的に参加しようとしない群衆に絶望を感じる一方で、その高邁(こうまい)な理想が、民衆のささやかな希望を奪い、日常を混乱に陥らせるという隘路(あいろ)に立たされた魯迅は、自らの希望が目の前の現実から目を背けさせる危険とも背中合わせであることに鈍感ではいられなかったのでしょう。