仏教教育センター
きょうのことば
きょうのことば 2026年2月
よし、それじゃあ僕は地獄へ行こう
SEARCH
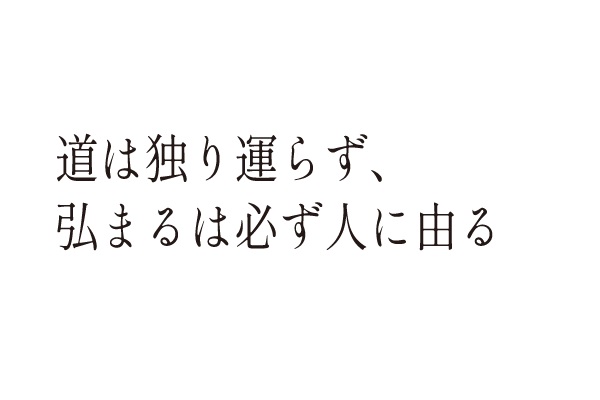
道は独り運(めぐ)らず、弘まるは必ず人に由る
僧衛「十住経含注序」『出三蔵記集』 (『大正新脩大蔵経』第 55 巻 61 頁)
6世紀の初めに中国で成立した現存最古の仏典目録『出三蔵記集(しゅつさんぞうきしゅう)』という書物があります。この時期は中国全土で仏教がひろまり始めた時期にあたり、その素晴らしい教えに心を動かされる人が増えていました。仏教に感動する人が増えると、その仏教というものがどのように興(おこ)り、どのように伝えられて来たのかということに関心を持つ人も多くなってきます。そのような関心に応えたのが『出三蔵記集』でした。
『出三蔵記集』は、単なる仏典( 経(きょう)・律(りつ)・論(ろん)の三蔵(さんぞう ))のリストにとどまりません。仏典は、もとインドや西域の言葉で表されていました。それを、長い道のりを経て中国にもたらし、中国語に翻訳するという大事業を成し遂げた法師たちがいました。『出三蔵記集』には、そういった人びとの伝記やそれらの仏典に付された序文なども収めています。標記のことばも、そのような序文の中に出てくるものです。
冒頭の「道」とは、ここではブッダの「教え」を意味しています。教えはそれだけでは伝播しません。教えがひろまっていくためには、その教えを大切な真実と受けとめて自ら実践し、さらに他のひとびとに伝えようとする「人」の地道な努力がなくてはなりません。仏教に限らず、「道」と呼ばれるような素晴らしいものが、社会に出現し、ひろく普及して定着するには、「人」のはたらきが欠かせません。私たちの周りには多くの素晴らしいものごとがありますが、普段の生活の中では、それらのひろまりと存続を支えてきた多くの人々のはたらきが十分に認識されていないのではないでしょうか。
私たちの身の周りにあるすべての素晴らしい「道」は、誰かが見出してその意義を分かりやすく説き、その「道」を多くの人が実践していけるような仕組みを作り上げ、実際にその運営に携わることによって成り立っています。
標記のことばは、私たちの周囲にある「道」は、自然にそこにあるのではなく、必ず人によってもたらされ維持されてきているということを、改めて思い起こさせてくれるものです。