仏教教育センター
きょうのことば
きょうのことば 2026年3月
一切衆生病むを以て、是の故に我も病む。
SEARCH
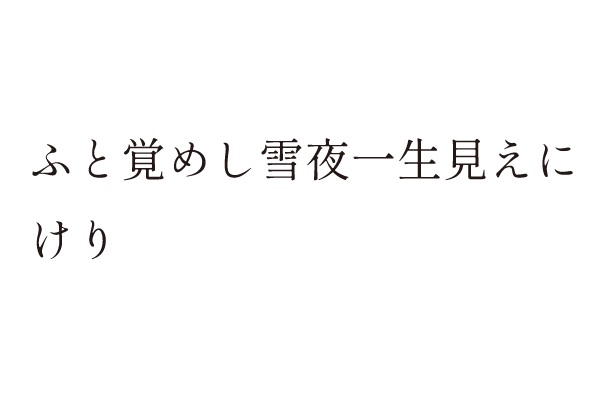
ふと覚めし雪夜一生見えにけり
もう40年近く前、大学に入ってはじめて住んだ京都には、当時よく雪が積もりました。雪国の方はもちろんご存じでしょうが、雪が降る夜というのは不思議な静けさに包まれています。それは、まるで音のない音とでもいったような深い静けさです。学生時代、すべてを吸い込むような静寂にふと気がついて深夜に窓の外を見ると、真っ暗な空から大きな雪片が次々と舞い落ちるのに気づいて、南国で育った私は息をのみました。
この「ふと覚めし雪夜一生見えにけり」という句は、そんな雪の夜を詠ったものです。人にはごくまれに「全体」を一挙に掴んでしまうような瞬間があります。いや、「全体を掴む」のではなく、むしろ逆に「全体から掴まれる」と言った方が正確かもしれません。しんしんと雪が降る冷たい夜、その果てしない無音にふと目が覚めた瞬間、自分自身の来し方行く末のすべてが一挙に見える。自分の一生という「全体」が見え、その全体に自分がぐっと捕らえられているのが見える。そういう恐ろしく美しい瞬間を、この俳句は詠っているように私はまず感じました。ですが、この句の作者である村越化石(1922-2014)の「一生」を知った時、この句がもつ静謐と深さはさらに底知れぬものになりました。
「化石」という名は俳号で、彼の本名は村越英彦といいます。英彦は16歳でハンセン病の宣告を受け、故郷を離れて群馬県草津市の国立療養所で生涯を送りました。「化石」という俳号について、彼は後にこう語っています——「故郷に帰ることもできない、世の中に出て暮らすこともできない、生きながらにして土の中に埋もれ、すでに石と化した物体のような自分を「化石」になぞらえて名付けたんだよ」。彼は40代の終わりに薬の副作用から全盲となり(この句はおそらくその頃詠まれたものでしょう)、長い年月の間に両手が不自由となって、聴力も失われていきます。
村越化石が「見えにけり」と詠った彼の一生は、私たちの一生とは比較にならないものです。しかし、私が強調したいのは、私たちとはかけ離れた彼の一生の「内容」のすさまじさではありません。むしろ逆に、彼が彼の一生という「全体」によってぐっと掴まれた瞬間があったように、私たちは私たちなりに、それぞれの人生において、きっといつか自分だけのどうにもならない一生に掴まれる瞬間を経験することがあるのではないでしょうか。この句には、その瞬間にただ一人真っすぐに向かい合った、村越化石という私たちと同じ一人の人間の誠実が響いています。それは雪夜のあの静謐のような人間の奥深さです。私が打たれたのはそのことでした。「ふと覚めし雪夜一生見えにけり」という短い句には、人が自分の一生という「全体」に向かい合って、そこから目を逸らすことなく端座する瞬間が見事に示されています。その身震いのするような静謐は、この句を読む者の姿勢を正すと同時に、「お前はどうなのだ」とひそかに問うているように私には思えます。