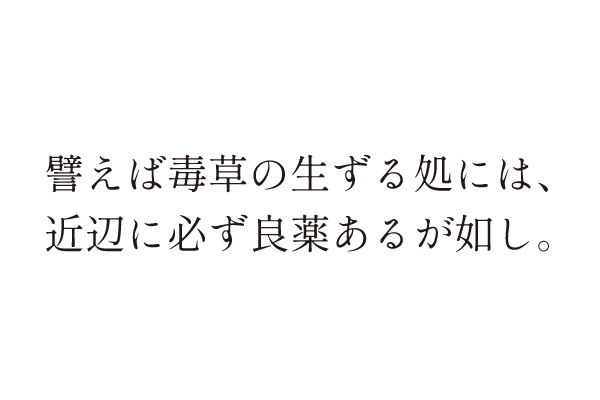仏典は、さまざまな譬喩(ひゆ)(たとえ)や物語によって、教えの内容を分かりやすく伝えようとしています。標題のことばの出典である『大智度論』は、『般若経』の注釈書であり、古代インドの龍樹が著したと伝えられています。この『大智度論』もさまざまな譬喩によって経典の内容を解説しています。
仏教の経典は、多くの場合「如是我聞(このように私は聞きました)」という文言から始まります。『大智度論』は経典の注釈書ですから、まずこの言葉の解説をします。経典では「如是我聞」に続いて、釈尊がどこでその教えを説いたのか、その場にどのくらいの仏弟子たちが集まっていたのか、そして主な仏弟子が誰だったのかが記されます。標題のことばは、釈尊が教えを説いた場所である「王舎城」という都市について説明する文脈に登場します。
「王舎城」は、古代インドの大国・マガダ国の首都であり、商工業の発達とともに多くの人々が集まる大都市だったようです。釈尊の時代、そのマガダ国の王は、仏典にも登場するビンビサーラでした。成道後の釈尊が、千二百五十人の仏弟子を連れて王舎城にやってきた際には、ビンビサーラ王は国民とともに釈尊と仏弟子たちを歓迎しました。そして竹林精舎を寄進するなど、釈尊に深く帰依した国王として知られています。
しかし、多くの人々が集まる大都市であるが故に、王舎城の全ての人が釈尊の教えを仰いでいたわけではなかったようです。釈尊の教えを論難する者、釈尊に嫉妬して反逆しようとする者、釈尊の教えとは異なる道を歩もうとする者たちも多くいたと『大智度論』は伝えています。それにもかかわらず、どうして釈尊はこの王舎城で教えを説いたのか、『大智度論』はこのような問いを立て、それに答える形で標題のことばを述べています。すなわち、「毒草が多く生える地にこそ、その近くに必ず良薬があるのだ」と。
釈尊が毒草の多く生える地に仏法を説き示そうとしたことは、現代における仏教のあり方とも関係しています。現代社会は、時に人間の都合のみが優先され、環境問題、国際関係などさまざまな分野において、多様な問題を生じています。問題が多ければこそ、人々は良薬を求めるでしょう。
現代社会の諸問題の解決には、表面的な組織や制度の改革のみでは対応できません。問題のより深い根元には、人間のものの見方・考え方があります。問題が多い時代・社会であるからこそ、人間が正しいものの見方・考え方をすることによって、世の中の誤った方向性を是正していかなければなりません。毒草が多く生い茂る時代であるからこそ、仏教が世の中に開かれていく意義があるのではないでしょうか。