仏教教育センター
きょうのことば
きょうのことば 2026年2月
よし、それじゃあ僕は地獄へ行こう
SEARCH
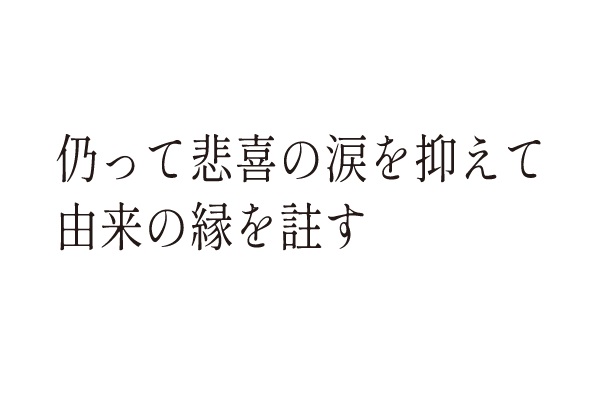
仍(よ)って悲喜の涙を抑えて
由来の縁を註(しる)す
親鸞(1173~1262)は、『教行信証』のむすび、いわゆる「後序(ごじょ)」に、人生を決定づけた自身の体験を記しています。一つは、承元(じょうげん)の法難と、師である法然との別離です。この法難で法然は土佐、親鸞は越後に流罪の身となり、それが今生の別れとなりました。もう一つは、法然との出会いと、その主著である『選択本願念仏集』の書写が許され、念仏の教えの相承を託されたことです。そして、「悲喜の涙を抑えて由来の縁を註す」と、これらの出来事が『教行信証』を著す「由来の縁」となったことが述べられています。
親鸞にとって、この二つの体験は、言葉ではあらわすことのできない悲しみと喜びであったに違いありません。そのことが「悲喜の涙を抑えて」と吐露されているのでしょう。しかし、その涙が涙で終わることはありませんでした。その涙こそが、自身が賜った師恩、さらには仏恩への深い感謝を呼び覚まし、生涯をかけて『教行信証』を著す原動力となったのです。それは自身の体験を、感傷的な涙を流すことで風化させるのではなく、涙のわけを自身の内に問い続ける歩みであったといえます。
ここで、「悲喜の涙」とは、「悲」と「喜」の涙というように、二種類の涙をいうのでしょうか。私たちは身に起こった出来事を、白黒を付けるかのように自分の都合で価値づけしていないでしょうか。まるで悲しい出来事には価値がなく、喜ばしい出来事には価値があるかのように。
しかし、人生の一場面や出来事を切り取って、これは「悲」、これは「喜」と簡単に分けることなどできるでしょうか。試合に勝利できた歓喜の背景には苦しい練習に耐えてきた悲しみが内包されているはずです。また、愛する人との別離が深い悲しみとなるのは、その人との出会いが本当の喜びであったからであり、別れによってはじめて出会いのかけがえのなさに気づかされることもしばしばです。そう考えると、私たちが経験する悲しみと喜びは実は表裏一体のものなのでしょう。
人には涙でしか表現できない悲しみや喜びがきっと訪れます。そんなとき、親鸞がそうであったように、自身の涙の意味を問うことで、人生のすべてが自分を歩ませる得難い経験として頷(うなづ)かれてくるに違いありません。そう考えると、目が涙に覆われて視界がにじむ経験は、いのち輝く世界が眼前に開けるための大切な機縁といえるのかもしれません。