仏教教育センター
きょうのことば
きょうのことば 2026年2月
よし、それじゃあ僕は地獄へ行こう
SEARCH
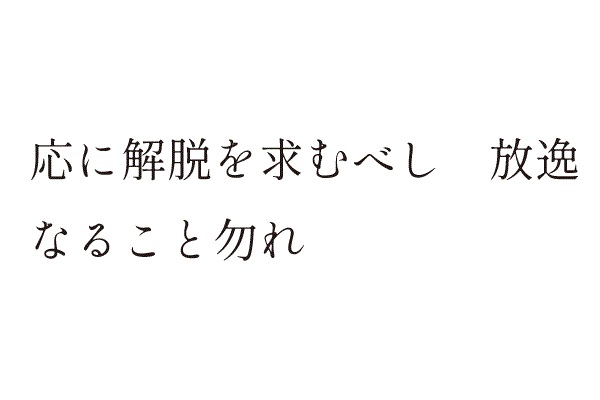
応に解脱を求むべし 放逸なること勿れ
五世紀のインドに登場した仏教思想家である世親(せしん)<ヴァスバンドゥ/天親(てんじん)>は『阿毘達磨倶舎論(あびだつまくしゃろん)』という書物を著しました。この書物の第8章「定品(じょうほん)」の最後には、論書を締めくくる文章の一節として標題のことばが記されています。解脱とは、苦しみの超克を意味します。それは、もはや苦しみを苦しみと言う必要がなくなったことを表します。放逸(ほういつ)とは、ほしいままに楽しむことを意味します。苦しみの超克を求める者たちは、ほしいままに楽しむことのないように歩まねばならないと、著者である世親が書き記しているのです。
ほしいままに楽しむことのないように歩まねばならないという表現は、釈尊のことばとして知られてきたものです。初期経典の『大般涅槃経(だいはつねはんぎょう)』に、釈尊の入滅について語られています。鍛冶工チュンダ<純陀(じゅんだ)>が用意した食事をとった釈尊は、激しい痛みにおそわれ、沙羅(さら)の木と木のあいだに身を横たえると、「形あるものは滅びゆくものである。不放逸に努めなさい」ということばを残して、その生涯を閉じていかれました。「これが如来の最後のことばであった」と『大般涅槃経』に述べられています。諸行無常を説き、死すべきものであるという苦しみを受けねばならないという真実と真正面から向きあい、ほしいままに楽しむことなく道を達成しなさいと釈尊は言い残されました。
人間は苦しみの存在である。この自覚が仏道の歩みの出発点であると言えます。しかし、なかなかこうした自覚の上に立つことができません。自分に不都合な事実に目を背け、あるいはそれを覆い隠そうとして、ほしいままに自分の楽しみをどこまでも追い求めるという態度をとってしまうことがあります。どこで私たちは苦しみの存在であるという自覚に立つことができるのか。たとえ今まさに命を終えようとも、不放逸に努めることこそが人間としてなすべきことであると、仏典には語られているのです。苦しみの自覚に立って歩もうという姿勢を保ち、その位置に踏みとどまり、そこから決して撤退しない。釈尊が最後に残したことばは、こうした歩みの姿勢に関わることばだったと受けとめておかなければなりません。そして、釈尊がまさにその生涯を閉じようという時に語られたこのことばを、世親もまた『阿毘達磨倶舎論』という大著を締めくくるにあたり用いているのです。
老病死の苦しみによって人生の支えだと考えてきたものが崩壊して疑いの渦中に投げ出されてしまった時、ほしいままに楽しむということで苦しみから逃れようとするのとは別の態度がある。このことがいつも仏教の思索の中心に据えられています。10月13日には開学記念日を迎え、開学記念式典並びに初代学長清沢満之謝徳法要を勤めます。苦しみの存在である私たちがいかに生きるべきかを求め続ける精神を大切にする場所として、大谷大学が開かれてきたことを確認する機会でありましょう。