仏教教育センター
きょうのことば
きょうのことば 2026年2月
よし、それじゃあ僕は地獄へ行こう
SEARCH
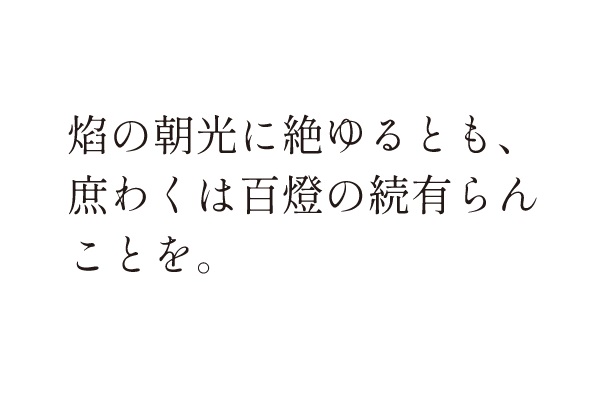
焰(ほのお)の朝光に絶(た)ゆるとも、庶(ねが)わくは百燈の続有らんことを。
3月は卒業式の季節です。卒業生は、大学を卒業して人生の新たなステージへと進んでいきます。長いようで短かった大学生活はどうでしたか。また、在学生の人も、この一年間、どのように過ごしましたか。節目となるこの季節に、これまでの大学生活、あるいはこの一年間の自分を振り返ってみてはいかがでしょうか。
標題のことばは、インドに仏法を求めて旅をした中国人僧・義浄(635-713)の『南海寄帰内法伝』という書物にあります。インドで起こった仏教は、アジアを中心に世界へ広がりました。しかしその教えは自動的に広まったわけではありません。特にインドから中国へと仏教が伝来する過程には、険しい山脈や過酷な砂漠を超えて、仏典を伝え、しかもそれらを翻訳して、異なる文化圏へと伝え広めた〈人〉の存在があったことを忘れてはなりません。
かつて中国には、399 年に六十歳を過ぎた老齢でありながらインドへと向かった法顕や、七世紀・唐代初期の玄奘など、有名な訳経僧が多くいました。義浄は、若い頃から法顕や玄奘の業績を仰ぎ慕い、自らもまたインドの地に足を踏み入れようと志します。義浄は 37 歳のとき、広州を出発し、南海を経由してインドへ向かいました。そして 695 年に帰国し、多くの仏典を伝えて翻訳活動に従事しました。
義浄のインドへの求法の旅は、行きも帰りも南海経由の海路でした。しかし海であっても、危険は常に隣り合わせです。数々の危機を乗り越えて若い頃から懐いていた目的を成就し、仏教界にもたらした義浄の功績は誠に偉大なものでありました。しかし義浄は、それを誇示するのではなく、自分が成し遂げた功績はかすかな灯明のようであると言います。しかもそれは、標題のことばにあるように、朝日が昇ればかき消されてしまうほどかすかなものであると述べます。しかし、わずかな灯火でも、それは別のもう一つの灯明となって受け継がれ、やがて百にも千にもなって、世間を照らしていくことがあるでしょう。
大学での学問も、すぐに成果となって表れるものばかりではありません。しかし、大学で学んだことや、疑問に感じたことを大切にしてください。これからの長い人生の中で、 若い頃に懐いた問いに対する答えが見つかることもあるでしょう。たとえ、今それが小さな灯明でも、後にそれが大きな輝きとなって、皆さん自身を、そして世の中を照らしていくことを願っています。