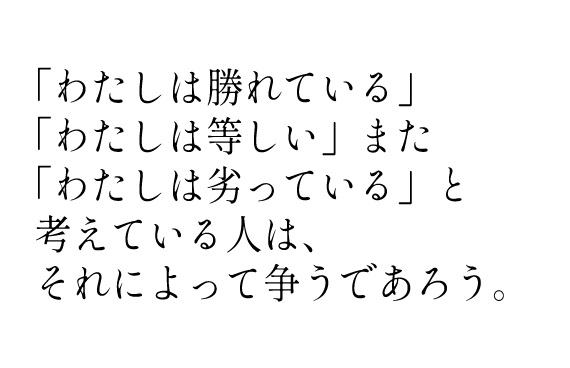ブッダは中道について語っています。中道とは、真ん中の道という意味ではなく、両極端を否定し、それを超えるということです。したがって、ここでは真ん中に相当する「等しい」ということも否定されています。両極端を超えるとは、判断したことに執着しないということです。勝敗、損得、善悪、上下、左右、好き嫌い、暑さ寒さなどという判断は、すべて相対的であり、人が言葉で行います。目の前の対象自体に、勝敗や損得などという本質が備わっているわけではありません。さらに、対象が判断するわけでもありません。判断は相対的であり、人によって異なります。
インドの例で言えば、目の前にいる毒蛇は、多くの人にとっては過去の経験からすれば苦痛でしかありません。しかし、職業としての蛇使いにとっては生活の糧であり、金儲けの手段なので、楽しみと判断できます。人によって、そしてその時の立場によって善悪や正義は異なります。お互いの判断が異なり、それがぶつかると争いになります。国家間の大きな争いは戦争です。ブッダの時代から現代に至るまでさまざまな形で戦争は続けられてきました。
言葉で表現される勝敗、優劣などの相対的なことに固執する人がいます。その人は言葉で表現される物事を理解しておらず、争いに巻き込まれます。しかし言葉で表現される物事は相対的であり、人によって、さらに時と場合によって異なるものであると理解しているならば、争いは起こりません。判断の結果として存在するようになった相対的な極端は、言葉に過ぎず、真に存在するものではありません。存在するという思い込みが生じ、それが勝れていると固執し、それ以外は劣っていると判断し、争いになるのです。
争いをなくすには、人は悪をなさず、欲望を捨て、よく気をつけるべきだと言われています(同 35 頁)。日常生活のなかで、まったく悪をなさないことやすべての欲望を完全に捨てることは不可能です。しかし、出来る限り悪をなさないように、少しでも欲望を減ずるように心がけ、自らの判断が相対的であることを意識して言動に「よく気をつける」ことはできるはずです。これは現代世界を生きる私たちに特に必要なことではないでしょうか。