仏教教育センター
きょうのことば
きょうのことば 2026年2月
よし、それじゃあ僕は地獄へ行こう
SEARCH
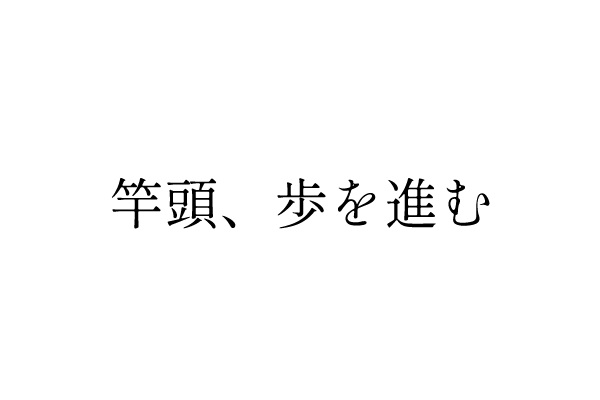
竿頭(かんとう)、歩を進む
禅宗、特に臨済(りんざい)宗や黄檗(おうばく)宗では、師から与えられた課題(公案)を考えながら精神集中(禅定)を行う修行方法が採られます(看話(かんな)禅)。公案は、一般的な感覚ではなかなか理解できないような内容であることが多く、師と弟子以外から見ると、噛み合わない会話のように感じられることもあります。「両手を打ち合わせると音がするが、片方の手にはどのような音があるのか」(隻手の声)などが有名です。中国の宋代(1127~1279 年)には、こういった公案を集めた公案集が多く編纂されました。『碧巌録(へきがんろく)』や『無門関』などが有名です。
標記の言葉は、『無門関』の第 46 則として取りあげられているものです。もとは唐代の長沙景岑(けいしん)(788~868 年)の言葉だとされています。この公案は、他にも多くの公案集に取りあげられています。
100 尺(およそ 30 メートル以上)もある竿を進み、その先端まで到達したとします。この公案では、「その竿の先端から更に一歩進みなさい」と問いかけています。
もうすでに先っぽにいるのですから、それ以上進むことはできません。むしろ、落ちることのないようにとしがみついてしまうことでしょう。無理に進んだならば、それまでに達成したことを失うばかりではなく、落ちて大怪我をしてしまうかも知れません。そう思うと、しがみつく手にますます力が入ってしまうことでしょう。このとき、竿にしがみつく人は、自らが達成したことに縛られているのです。この公案は、そのような姿勢を厳しく批判します。
100 尺の竿は仏道を譬えています。仏道に達する効果の一つとして自由となることが挙げられます。自由とは、何ものにも由(よ)らず、自ら自身に由ることを指します。
長い竿(修行過程)を進むことは容易ではありません。それだけに、先端まで進むことができたならばそれだけで満足してしまいそうです。しかしながら、それは仏道の完成ではありません。それまでやってきたことをただ延長するだけでは、先端の更に先に踏み出すことはできません。
この公案は、「それまでの積み重ねてきた努力の上に、更に尽力すること」と解説されることもあります。しかしながら、この公案が伝えたいのは、むしろそれまでの努力を単純に積み重ねるだけでは、本当の目的に到達することはできないということです。竿の先端にまで辿り着くことができたという自らの成果にしがみついているからです。
長い竿の先端にまで進みながらも、その成果に執着することなく、自由に新たな一歩を踏み出せるということの重要性が示されています。