仏教教育センター
きょうのことば
きょうのことば 2026年2月
よし、それじゃあ僕は地獄へ行こう
SEARCH
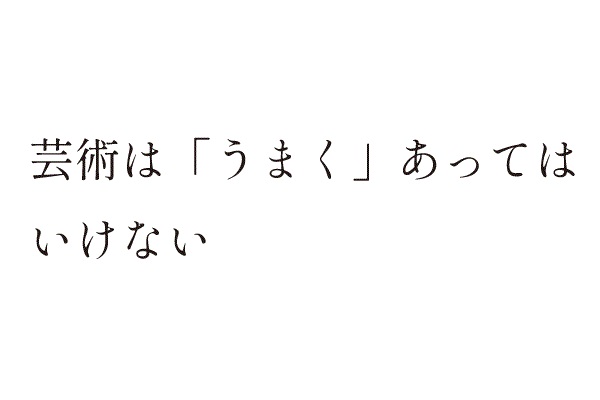
芸術は「うまく」あってはいけない
なぜ芸術は「うまく」てはダメなのでしょうか。岡本が67年前に主張したこの命題について、皆さん自身の経験につなげて考えて頂きたいのです。皆さんは、学校の美術教育を受けた(又は今も受けている)経験がおありかと思います。しかし成人になって美術が苦手、嫌いだと言う人は意外と多いのです。なぜかと聞くと、「うまくないから」、「才能がないから」とおっしゃる。つまり、うまければ好きになっているはずだというわけです。しかし、そもそも「うまくない」と思う根拠は何でしょうか。その多くは、自分がそう判断したからという以上に、友達や先生など周りの評価でそう"思わされてきた"のではないでしょうか。この事に関連して岡本は、同じ一枚の絵でもそれを見る受け手によって評価は変わる。だから「受け手によって作品は死にもするし、輝きもする」と言っています。
そこで岡本は、次のような西洋美術史の話をします─
それゆえ、彼らの出現こそが近代芸術の進展の大転換だったと岡本は言います。では、なぜこのような大転換が起こったのか。岡本は、それを「個人の自由を自他ともにみとめ、許したという市民社会の新しい雰囲気」、これこそが「市民芸術を完成した絶対条件」なのだと言いました。そして「こんな話は、けっしてよそごとではありません」と、海外の画家の話にとどまらず、当時の日本の状況と大きく関係しているのだと主張したのです。なぜなら戦後においても、アカデミックな権威がはびこっていて、それは一般市民の価値観の中にまで根強く影響を及ぼしているからだと。その価値観は、まさに岡本が否定した「うまい絵」こそがいいのだという作品の見方でした。
どうでしょうか。なぜ岡本が芸術は「うまく」あってはいけないと主張したのかお分かりでしょうか。では、現代の私たちの生活には、はたして「個人の自由を自他ともにみとめ、許した新しい雰囲気」はあるでしょうか。必ずしもあるとは言えないことも多いのではないでしょうか。そんな個人の表現の自由度をはかる一つのメルクマールが、私たちの美術やその他の芸術への理解・見方にあると思うのです。
誰か、周りの人が描いた絵や作品を見かけたとき、いつもよりその作品がもつ個性やいい所を見つけて、誉めてあげませんか?うまいかどうかという基準以外の見方で互いの作品を認め合えるようになれば、岡本が願っていた“普通の人々による表現活動”が、より創造的で豊かになるはずです。そしてそれは、充実した人生そのものをつくることでもあります。岡本の言葉には、芸術を通したそんな理想が込められているのです。