仏教教育センター
きょうのことば
きょうのことば 2026年2月
よし、それじゃあ僕は地獄へ行こう
SEARCH
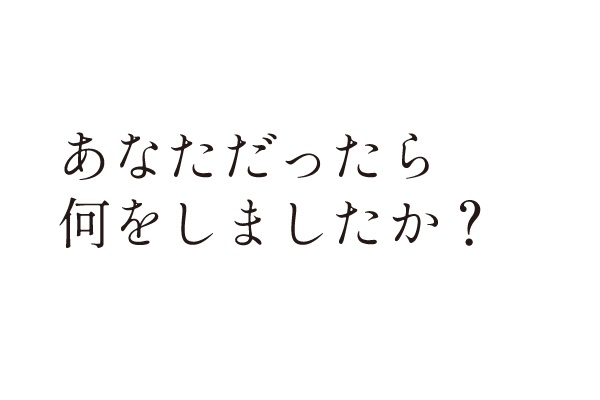
あなただったら何をしましたか?
このことばが語られる『朗読者』という小説にはとても重い背景があります。それは第二次世界大戦でのユダヤ人虐殺という戦争犯罪です。さらに、そこには親の世代の戦争犯罪をその後の世代がどのように受け止めていくかという複雑で難しい問題も重なっています。しかし、今回着目したいのはそれとは少し違う事柄です。ここで取り上げるのは、私たちと同じように愚かで弱い、それでも何とか必死に生きて行こうとするごく普通の生真面目な一人の女性が、たまたま何かの拍子に少し道を逸(そ)れ(逸れたことにさえほとんど気づかず)、ふと気がつくと取り返しのつかない場所に立っている、その偶然の恐ろしさです。
この女性(ハンナ)にはどうしても言えないある秘密がありました。それは決して彼女が自分の咎(とが)で抱えた秘密ではありません。この悲しい秘密を、他人の迷惑にならないように、そして自分の誇りも傷つかないようにそっと隠し続けた結果、彼女はユダヤ人収容所の看守となり、やがて目の前で何百人という人々が焼け死ぬのを放置する加害者となります。しかし、被告として法廷に立ったハンナはやはりその秘密を話すことはできませんでした。それは彼女に残された人としての最後のプライドだったからです。
すべてが終わった地点に立ってハンナを眺める私たちは、何とでも言うことができます。なぜそんな秘密にこだわったのか。その秘密は彼女のせいではないが、努力すれば克服できたのではないか。その通りです。ほんの少し何かを変えていれば、彼女は加害者になることはなかった。彼女の罪は真っ当に裁かれるべきです。それでも、と私は思います。自分が今抱えている小さな弱さや愚かさ、誰に迷惑をかけるでもない悪気のない嘘が、いつか偶然に弄ばれて恐ろしい出来事に行き着くなどと、現在の私にいったいどうして想像できるでしょう。ハンナもそうだったのではないでしょうか。そうだとしたら、後から見たら取り返しのつかない流れの中に、じつは私ももう巻き込まれてしまっているのかもしれません。
「あなただったら何をしましたか」—これは収容所での罪を問われたハンナが、逆に裁判長へ真剣に問いかけたことばです。これは決してハンナの「反論」ではありません。彼女は自分の罪を軽くしてもらうためにこう尋ねたのではありません。この問いかけは小説の中で二度現れますが、二度目にはほとんど響かず、皆に無視されてしまいます。それはおそらく、人がこの問いそのものを聞かなかったことにしたいからです。私たちは「こんな恐ろしい出来事は自分には(自分にだけは)起こらない」と信じたいのです。それでもやはり、この問いかけが生じる場所に耳を澄ませねばならないと私は思います。私たちはこの声を聴かねばなりません。それは決して罪を減ずるということではありません。加害者の罪を罪として裁きながらも同時にこの声を聴くという矛盾の中に、そこで起こった筆舌に尽くしがたい恐ろしい出来事に本当に向かい合うただひとつの可能性が賭けられているのだと私は思います。