仏教学科
卒業生インタビュー
SEARCH
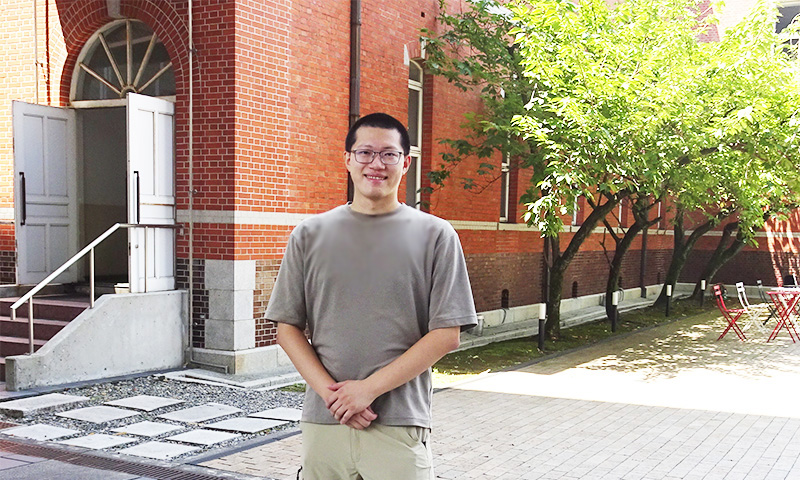
現在文学部仏教学科現代仏教コースで学んでいるLIN CHINGHSINGさんに、仏教学科での学びについて語っていただきました。
※このページに掲載されている内容は、取材当時(2023年7月)のものです。

私は、仏教を学ぶため大谷大学に進学しました。台湾でも仏教はとても盛んです。多くの仏教寺院があり、人々が日常的に参拝しています。私自身もそのような雰囲気の中で育ったので、子供の頃から気軽に親と一緒にお寺に通っていました。だから、仏教のことは自然に受け取れます。
小学校最終学年の夏休み頃に、池坊(いけのぼう)と出会いました。池坊は日本のいけばなの源流とも言えるものですが、日本のみではなく世界各地で活動しています。もちろん、台湾でも池坊は盛んに活動しています。私が池坊の教室に通うようになったのは、母の勧めによるものでした。母は、私が四季を意識して美意識を高めるのに役に立つだろうと、いけばなを習ってはどうかと勧めてきたのです。
台湾池坊でいけばなを習っている時に、お寺に供花する際の助手を務めさせてもらうという経験をしました。教室の先輩に熱心な仏教信者がいて、その縁で法要の際に供花するよう依頼をいただいたのです。その助手を務められるというのは、たいへん名誉なことです。助手を務めながら、先生が供花を立てている様子を間近で見ていました。その時、お花が供えられたお寺に漂っていた荘厳な雰囲気にぞっとするほどの大きな衝撃を受けました。日本語の「ぞっとする」という表現は、恐ろしい思いをした時などに鳥肌が立つような感じがすることを指すようです。その時の私は恐ろしかったわけではありませんが、鳥肌が立つほどに体温が大きく変化したように感じたのです。いけばなと仏教との関係を私が強く感じたのは、いま思い起こすと、この時だったのかも知れません。

大学卒業後、兵役を終え、池坊の神髄をもっと探究しようと考えました。台湾の日本語学校でしばらく学び、来日して池坊短期大学に入学しました。池坊短期大学在学中に『池坊専応口伝』序文を読む機会がありました。
『池坊専応口伝』は、池坊専応(1482-1543)による口伝を記したもので、華道を理論的に体系化したとされる重要な文献です。これを読むと、仏教の素養を身につけていないと半分ぐらいしか意味が分からないことに気がつきました。それでも、理解できる部分だけからでも、興味はますます募りました。
『池坊専応口伝』序文の内容をより深く理解するためには、仏教のことを知らなくてはできません。仏教を学ぶならと、大谷大学に進学しました。

仏教学科に入学してからは、仏教の経典ばかりではなく、日本や中国の仏教史を学びました。その中で、宗教的な視点はもちろん、学術的な方法、批判的な(時には「否定的な」)視点までも含めて、さまざまな視点から仏教を見ることができるのだと知りました。ものごころついた時から仏教に触れていた私にとって、それはとても新鮮でした。
例えば、神話の時代から日本の歴史を説く『古事記』という書物の視点から、日本が仏教を受け容れた物語をはじめ、日本古来の神々と仏教とが習合した面白い物語をたくさん知ることができました。また、「日本仏教史」という授業では、政治的な視点から日本仏教の展開を見るということを学びました。仏教は、ある時代には最先端の技術や文化であり、また別の時代には権力者による民衆統治の手段であったといいます。

専応より少し遅れて、日本では千利休(1522-1591)が茶道を確立しました。茶道も、日本では仏教と無関係ではありませんでした。「利休七則」と呼ばれるものの中に「花は野にあるように」と言われています。茶席では、野に咲いているように花を活けるべきだというのです。「野に咲いている〈ままに〉」ではありません。池坊では、草木を撓めたり加工を施すことによって、却って「野」を表現しようとします。加工されたものの方が自然を表現できるのです。これは、仏ならざる私たちはありのままには「野の花」を見ていないという、仏教の考え方が影響しています。
そもそも、池坊のいけばなは、頂法寺(六角堂)で仏前に花を供えてきたことが起源です。仏を荘厳することがいけばなの根底にあるのですから、仏教と無関係でいられるはずがありません。
このように、大谷大学の授業では、単に知識を得るだけではなく、それら知識を通じて新しい視点を得ることができたように思います。そういったさまざまな視点から、改めて仏教とはどういうものなのかを考えることができるようになりました。このような学びは、当然ながら私のいけばなに対する考え方にも影響しているように感じています。今後も生涯にわたっていけばなと関わっていくつもりですので、仏教を学んだことは私の生涯全体に影響を与えたということになります。


林 景星/LIN CHINGHSING (リン ジンシン)
文学部 仏教学科 現代仏教コース 第4学年