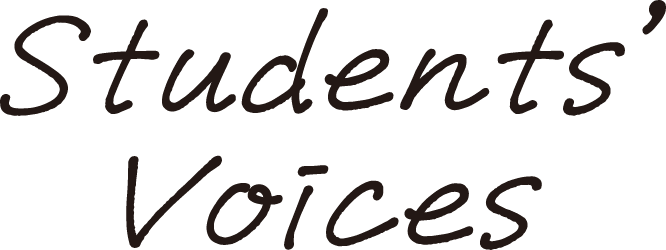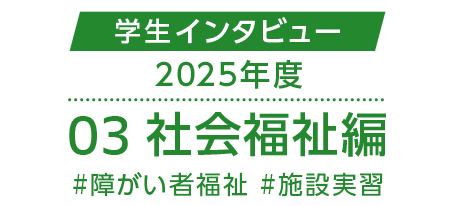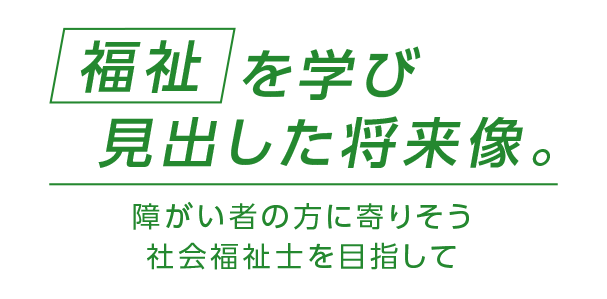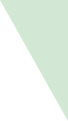アクティブな学びから
福祉の仕事の本質を捉える
大学の授業は、教壇の先生が話すのを聞いてノートを取るだけと思っていましたが、違っていて、いい意味でギャップを感じました。実際は、仲間と一緒に活動したり意見を交わしたりするグループワークやディスカッションの機会が多く、学外に出て活動するフィールドワークや施設実習も充実していて、アクティブに学べます。
なかでも広い視点で考えられるようになったのは、2年生の時に取り組んだ「地域連携室(コミュ・ラボ)」での活動です。具体的には地域に直接出向いて課題解決の方策を考えるフィールドワークで、私は京都府北部の山間地域にある介護事業所と社会福祉協議会を訪問しました。そのとき、高齢化の進行や交通手段の不足などの理由から、必要な支援が十分に受けられない人がいるという現実を知り、地域によって異なる実情にも目を向けて福祉のあり方を考える大切さを学びました。
さらに、障がい者支援施設などで計240時間の施設実習に取り組んだことで、より広い視野で福祉を捉えられるようになったと思います。振り返ると、入学前の私は「福祉の仕事」を限定的に解釈していました。困りごとやハンディキャップを抱えた方の「できないこと」を手助けするだけのイメージを持っていたんです。でも、施設実習を経て、福祉の仕事は社会的弱者の方に寄りそうことであり、その方のやりたいことは何か、どうすれば実現できるか想像力を働かせ、創意工夫を凝らすことが必要だと気づきました。実は、すごくクリエイティブなんですよね。そういう考え方やスキルを身につけられたのは、自分の成長を一番実感する部分です。
私は、子ども食堂でボランティア活動もしていますが、子どもたちが安心して過ごせる居場所をつくるうえで、施設実習で培ったことにも通じる「一人ひとりの気持ちや個性を見極める力」の重要性を強く感じます。