教員
教員コラム
教員コラム「仏教あれこれ」
2025年12月 文学部 仏教学科 教授 箕浦 暁雄
SEARCH
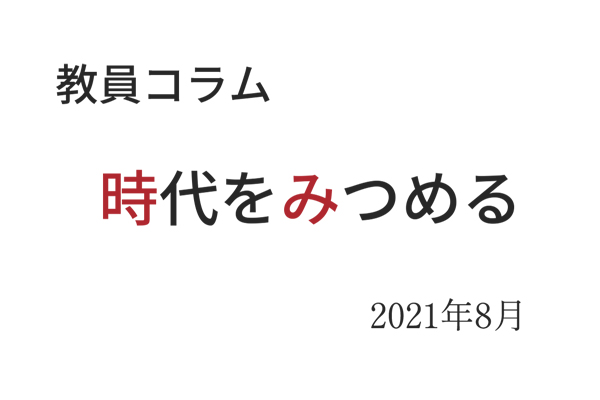
コロナ禍のさなかに読んだ仏教経典に、このようなことばを見つけた。「わたしは病いの性質(dharma)をもっている。わたしが病いの性質を克服することはない。この事実を繰り返し省察せよ」というブッダのことばである。
新型コロナウイルス感染症の拡大は、その脅威から免れる者が誰ひとりとしていないという点で、人間が等しく病いの器である事実をまざまざと示した。
わたしの身体に生じる病いはわたしに固有のものでもある。したがって我が身に感染が及んだならば、我が身が病魔に襲われたならば、「どうして」と慨嘆せずにいられない。「どうしてわたしだけが」「どうしてわたしひとりだけが」という思考に囚われてしまうことを、ブッダは「自己を悩ます毒を含んだ憂いの矢」と呼んでいる。なお、その矢を射るのも射られるのも共に自分自身である。
先の経典は次のように続く。「しかし、わたしひとりだけが病いの性質をもち、病いの性質を克服しないのではない。そうではなくて、生きとし生けるものはみな、病いの性質をもち、病いの性質を克服することがないのだ」。仏教では、老病死する身体をもって生きているという事実を「苦」(duḥkha)という一語で言い表す。そしてブッダは、生きとし生けるものがみな老病死する身体をもって生きているという事実に立脚せよ、という。言うなれば、共苦(苦を共にすること)である。
もし、わたしたちが共苦という地平に立つことができるなら、ひとりひとりの苦が孤立することはない。そこに、苦をうけとめ、生きる意味の展開する契機があるのではないか。
2021年8月現在、新型コロナウイルス感染症の拡大は悪化の一途を辿っている。今はそれぞれの持ち場で静かに耐え忍ぶ以外にできることはないのかもしれない。そうした状況のなかで、孤立に陥らず、自分で自分を傷つける「憂いの矢」を避けるためにできることは何か。「わたしひとりではない」。ブッダは共苦という地平を指し示している。


上野 牧生 講師
【専門分野】
仏教学
【研究領域・テーマ】
インド仏教/阿含経典/ヴァスバンドゥ/世親/『釈軌論』