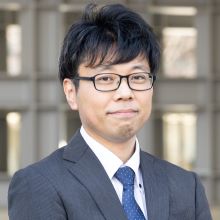
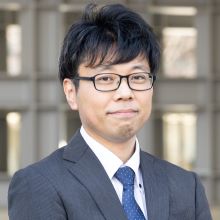
工藤 克洋 講師 KUDO Katsuhiro
- 専門分野
- 【日本中世史/博物館学芸員/歴史情報学】
博士(文学)
【研究領域・テーマ】
勧進/情報伝達/デジタルアーカイブ
研究内容
南北朝期や戦国期といった戦乱の時代に、各地の状況を伝える情報はどのように流通していたのかを皮切りに、情報の流通の一端を担った聖・山伏と言われる宗教者に行きつき、彼らが列島社会で展開していた勧進(募金)活動を追いかけています。また、博物館や公文書館、図書館での勤務経験があることから、文化財のデジタルアーカイブや書籍の検索システムなどのウェブシステムの構築に関心があり自作したりしています。
ゼミ紹介
好きな歴史を学びたいと思っていても、ふと就職のことを考えた時「社会のどんな場面で役に立つんだろう」と不安に思ったことはないですか?わたしも学生の頃に、親にその言葉を言われ、何も言い返すことができず悔しい思いをしたことがあります。しかし、社会に出てみれば、地域の歴史の復元や文化財の研究は、地域の活性化や観光ツールとても重要な位置を占めていますし、グッズの開発においても歴史とコラボしたものが多くあります。自分が明らかにしたい歴史が、どの地域に、どんな人に対して有益なのかを見つけることができれば、歴史を学ぶことに自信が持てるはずです。また、どのような社会で活躍したいかもみえてくるでしょう。みなさんが明らかにしたい歴史とそれが活かされる社会の接点を一緒にみつけていきましょう。
主な担当授業科目
歴史学演習/歴史学特殊講義/博物館実習/博物館展示論
所属学会
歴史学研究会/中世史研究会
経歴・活動歴
1982年神奈川県生まれ。大谷大学大学院文学研究科博士後期課程(仏教文化専攻)単位取得満期退学。博士(文学)。愛媛県歴史文化博物館(指定管理者イヨテツケーターサービス(株)所属学芸員)、大谷大学助教、滋賀県県史資料室(現、滋賀県公文書館)、同朋大学仏教文化研究所、京都産業大学大学史編纂事務室、今日庵文庫、明石市立文化博物館(指定管理者(株)小学館集英社プロダクション所属副館長兼学芸員)を経て、2025年に大谷大学文学部歴史学科に着任。
主要著書・論文
共著
- 本願寺教団と中近世社会
論文
- 秀吉と日吉社・延暦寺復興勧進
- 戦国期における愛宕山五坊・山伏の諸国勧進
- 中世の情報メディアとしてみる山伏
- 先達と認められなかった白山先達の檀那引
- 戦況情報と南北朝内乱
- 聖・山伏がうみだした戦国期の本願—多賀社本願不動院を事例として—

