きょうのことば - [2010年08月]
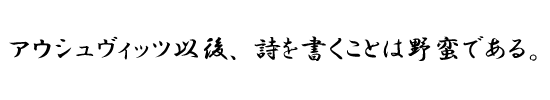
「アウシュヴィッツ以後、詩を書くことは野蛮である。」
アドルノ「文化批判と社会」(『プリズメン』ちくま学芸文庫 36頁)
テオドール・W・アドルノ(1903-69)は、ドイツの哲学者であり、ナチスの台頭を機にイギリス、アメリカに移り、戦後は再び生地フランクフルトに戻り、活動をつづけた人です。
標記のことばにでてくるアウシュヴィッツは、ナチスドイツがユダヤ人大量虐殺を実行した強制収容所の名前であり、そのことを示す代名詞のようにも使われています。しかしここでは、アウシュヴィッツを野蛮と表現しているのではなく、詩作が野蛮であるというのです。このことは何を意味しているのでしょう。
アドルノの思想にはさまざまな特徴がありますが、そのひとつが「文化批判」です。ここで指摘されているのは、物体として固定化され流通させられているものは文化ではないということであり、精神的活動こそがすなわち本来の文化であるということです。現代社会は、商品が流通しそれを購入する消費者がおり、そして言論自体もマスメディアを通じた一種の商品であるような社会ですが、この社会の枠組みをアドルノは批判しました。ここでいう批判とは、社会の枠組みそのものを問い直し、人間の姿を見つめ直す活動です。20世紀という時代は、効率化が推し進められた時代であるといえる一方で、その効率という枠組みそのものに人間の精神的な活動が浸食されていった時代であるともいえます。
そのような時代にあって、もともと自由な精神の活動であるはずの文化は、物として固定化された商品という形で流通し、それが「文化」であると誤ってみなされている、とアドルノは指摘します。文化は流通のなかにおいて「飼い馴らされて」いるのです。そこにおいては、この文化の現状を批判することもまた、一種の商品としての性質を帯びてしまい、批判としての機能を果たさないという皮肉な状況におかれています。
アウシュヴィッツという空前の事件は、効率性を中心に据えたという意味においてまさに20世紀という現代を象徴する出来事といえます。そしてこの野蛮の極致ともいえる事件は、まさに「文化」と見なされているその効率性から生じたものだったのです。アドルノによれば、文化とは野蛮の対極にあるものではなく、文化こそ野蛮との親和性を持つものであると理解されるのです。
そのような「文化」が引き起こしたアウシュヴィッツのあとで、文化の批判が根本的に為されないままに放置されるのであれば、アドルノが考える本来の意味の文化である「詩作」ですら、人間の活動からは最も離れたところにある野蛮さを体現しているといわざるを得ないのです。
