きょうのことば - [1999年06月]
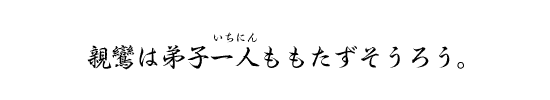
「親鸞は弟子一人ももたずそうろう。」
『歎 異 抄』『真宗聖典』628頁
どんなことを学ぶ場合も、よい先生に出会うことが、大事なことでしょう。自分が知らないことでも、そのことをよく知っている先生に学ぶことを通して、だんだんと知っていくことができます。自分にとって「先生」と呼べるような人と出会い、その人のもとで「生徒」として学ぶ、そのことを師弟関係を結ぶと言います。
師弟関係を通して学んでいくことは、お茶やお花などの習い事の道においても大切なことでしょう。自分の人生の道を学んでいくということにおいても極めて大切なことなのです。人生の道について、そのことを本当に知っている先生のもとで弟子として学んでいく、そんな師弟関係を仏教は大事な事柄として語っています。
そのような師弟関係においては、先生はあくまで先生ですし、弟子はどこまでも弟子で、両者は一線を画するものです。そこに「教える」ということも「学ぶ」ということも成り立つのです。
親鸞(1173~1262)の語りかけを通して、人生の大切な事柄に気付いていった人々が多く生まれました。『歎異抄』を著した唯円という人もその中の一人です。ですから、親鸞には「弟子」と呼んでもよいような人達が沢山いたわけです。それらの人達は、親鸞を仏教の「先生」として尊敬し、かつ慕っていました。
それにもかかわらず、親鸞自身は、自分は弟子を一人も持っていません、と語っているのです。これは一体どういうことなのでしょうか。
親鸞はその生涯において、力を尽くして、自身が仏教を学び続けていきました。そして同時に他の人に仏教を伝えていきました。しかし、そのように親鸞が学びかつ伝えていった仏教(浄土真宗)とは、自分の力によって信心を起こすものではありませんでした。また、自分の力によって他の人に信心を起こさせるというものでもなかったのです。
信心(真実の目覚め)とは、真実である如来のはたらきによってこそ起こる。そして、その真実の如来の前では、誰であろうとも一人の人間(煩悩具足の凡夫)という以外の何者でもない。そういう仏教に親鸞は出会ったのです。だから、人間関係の上では先生と弟子であっても、如来の前では丸裸の人間同士なのです。
そのような仏教に出会った親鸞は、自分は弟子を一人も持っていません、と言い切るのです。つまり、仏教を学んでいくうえにおいては、「先生」であろうが「弟子」であろうが、共に学び合っていく「友」(同朋)なのですよ、と親鸞は語っているのです。
