きょうのことば - [2019年08月]
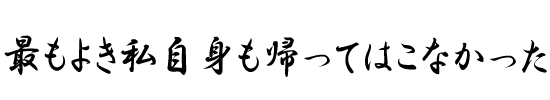
「最もよき私自身も帰ってはこなかった」
石原吉郎(『サンチョ・パンサの帰郷』思潮社 143頁)
8年間におよぶシベリア抑留から生還した詩人の石原吉郎(1915-1977)は、V.フランクルが『夜と霧』の序文に記した「すなわち最もよき人々は帰ってこなかった」という言葉を受けて、標記の言葉を書き添えました。第二次世界大戦中のナチスの強制収容所の生存者であるフランクルのこの言葉を、石原は疼(うず)くような思いで読んだといいます。
シベリアの強制収容所(ラーゲリ)に送られた石原は、氷点下40度にもなる極寒の地で、強制労働に従事させられました。強制収容所での食料供給は絶対的に不足し、重労働を課せられ痩せ衰えた肉体は、這いまわるような飢えに苦しんだといいます。栄養失調の過程は、文字どおり生命が自らの身体の蛋白質を食いつくし、筋肉組織を奪い去ります。劣悪な衛生環境も相まって、6万人ものシベリア抑留者が命を落としました。
こうした極限の状況を生き延びた後に石原やフランクルの心に重く伸し掛った感情は、生還したよろこびやうれしさよりも、罪責感やうしろめたさ、恥ずかしさでした。強制収容所の過酷な状況では、年老いた者や傷病者、子どもなどの弱者を助け支えた「最もよき人々」は、真っ先に倒れていったのです。わずかな食料を得るために必要なことは、仲間を裏切り、権力にへつらい、狡知をめぐらせることであり、自らの浅ましさや卑劣さになんら痛痒を感じないほどに人間性を堕落させることでした。強制収容所での苛烈な生存競争では、「いわば人間でなくなることへのためらいから、さいごまで自由になることのできなかった人たちから淘汰がはじまった」というのです(石原吉郎『望郷と海』みすず書房)。生存者が、責めや負い目、恥を感じずにはいられないのは、生き残ることが、他人の命を凌(しの)いだことに等しいからでした。たとえ強制収容所を生き延びたにせよ、「最もよき私自身」は二度と帰ってはこなかったのです。
強制収容所という惨禍には、紛うことのない被害者であっても、加害意識や罪責感を背負わされるという烈しい悲痛があります。しかし、客観的に見て、かれらに罪がない場合であっても、だからこそ、罪を感じる能力だけが、かれらに残された人間性の証になります。石原吉郎もフランクルも、自らの責任を終生、問い続けています。誤解してはならないことは、石原の思索は、被害者が互いの加害者にもなってしまうという悲劇をとおして、戦争の理不尽さを伝えることではないということです。自らの加害性に対して、戦争だったからやむを得なかったのだというような弁解は、欺瞞にほかならないことに石原は自覚的でした。強制収容所という極限状況にあっても、「最もよき人々」がそうであったように、人間であり続ける側に踏みとどまるかどうかは、一人ひとりの個人が向き合う問いとして残されていたからです。
石原の眼には、日本の戦後70年余りは、理不尽な戦争の犠牲者という被害者意識をもつことで、自分たちが加害者でもあったという事実から目を逸らし続けてきた社会に映っているのかもしれません。
